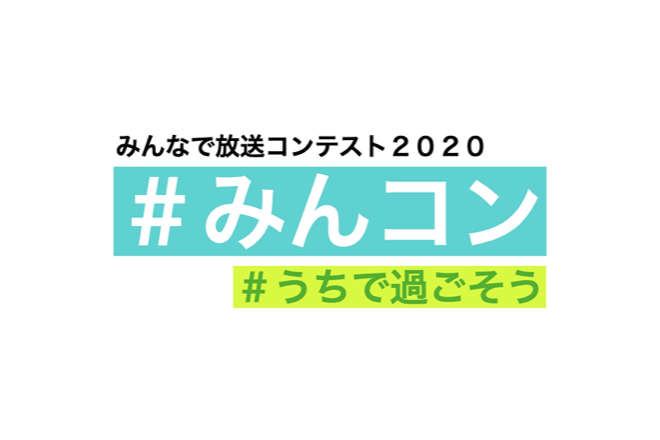アナウンス部門・朗読部門について
1. 参加者
応募は1人1作品のみです。アナウンス部門、朗読部門の両方に参加することはできません。また、参加資格を所有していれば放送部の方でなくても構いません。
2. 審査員
予選審査は各部門の参加者全員で審査を行います。審査するブロックはコンピューターによりランダムで選ばれます。参加人数によってうまく割り切れない場合は、OB・OGの審査員を追加する可能性があります。準決勝・決勝審査はOB・OG(全国大会入賞者)やアナウンサーの方をお招きして審査を行いたいと考えています。
3. 募集方法
ホームページで公開する応募フォームから音源等を提出してもらいます。原稿テンプレートも後日ホームページ上にて公開します。
4. 審査基準
基本的にNHK杯全国高校放送コンテストの審査基準を基に審査する予定です。
5. 審査方法
参加者が録音した音源、原稿、課題文(準決勝・決勝審査のみ)で審査します。
(i) 予選審査
予選審査の内容は本人が作成した原稿です。
参加者はいくつかのブロックに振り分けられ、運営はブロックごとに審査用の音源と参加者の情報を載せた動画を作成します。動画に載る情報はエントリーナンバー、出身の都道府県、名前(ニックネーム)に加え、アナウンス部門ではリード文、朗読部門では抽出箇所のあらすじです。動画はYouTube上に評価やコメントは見えない設定にして期間限定で公開予定です。(審査を行わなかった場合、ペナルティを課します。)
参加者は出場したブロック以外の動画を1つ視聴し、審査用紙に従って審査します。審査内容はデータで提出してもらいます。(審査基準は「アナウンス・朗読部門 審査基準について」に記載)
各ブロックで選ばれた12名の参加者が決勝審査に進出します。(参加者の数が規定数に達しなかった場合は、予選審査を省きます。)
(ii) 準決勝審査
準決勝審査の内容は本人が作成した原稿と運営で用意した課題文です。音源は予選審査で使用していない新しい録音データを提出してもらいます。
審査は準決勝進出者(最大 60 名)のデータを載せた動画を作成し YouTube のプレミア公開機能を使って動画を公開する予定です。準決勝審査の講評はそれぞれ準決勝進出者本人にデータでお送りします。(参加者の数が規定数に達しなかった場合は、準決勝審査を省きます。)
(iii) 決勝審査
決勝審査の内容は本人が作成した原稿と運営で用意した課題文です。
音源は予選・準決勝審査で使用していない新しい録音データを提出してもらいます。また課題文の内容は準決勝とは異なります。
審査はYouTubeライブにて生中継の審査を行うか、予選と同様決勝進出者12名のデータを載せた動画を作成しYouTube上に投稿しますYouTube のプレミア公開機能を使って動画を公開する予定です。準決勝・決勝審査の講評はそれぞれ決勝進出者本人にデータでお送りします。
(iv) 準決勝・決勝進出時の注意事項
準決勝審査の内容は本人が作成した原稿と運営で用意した課題文です。音源は予選審査で使用していない新しい録音データを提出してもらいます。
審査は準決勝進出者(最大 60 名)のデータを載せた動画を作成し YouTube のプレミア公開機能を使って動画を公開する予定です。準決勝審査の講評はそれぞれ準決勝進出者本人にデータでお送りします。(参加者の数が規定数に達しなかった場合は、準決勝審査を省きます。)
6. 提出物
- 収録音源(ファイル形式は検討中)
- 音源に対応する原稿
- (アナウンス部門はリード文と本文)
- (朗読部門はあらすじと本文)
朗読部門 規定
1. テーマ
本大会の朗読部門のテーマは「いま、あなたが伝えたいストーリー」です。
課題図書を指定せずに、青空文庫に掲載されている文章の中から朗読個所の選定を行ってもらいます。今年度Nコンの課題図書は著作権の問題で除外します。
2. 朗読部門規定
朗読のはじめにエントリーナンバー、名前(ニックネーム)、作者名(訳者名は読まない)、作品名を読み上げ、時間はそれらを含め1分30秒以上2分以内に読むことのできる原稿を作成してもらいます。さらに抽出箇所のあらすじを200字程度でまとめてもらいます。このあらすじは文章のみ提出していただきます。
提出書類は運営で準備するテンプレートに従って作成してもらいます。
なお録音音源は無加工の状態で提出して下さい。もしも編集した音源を提出した場合は失格とします。
現在全国の図書館が閉館し使用することができないなか、課題図書を指定することは難しいと考え、朗読作品はオンラインで閲覧可能な青空文庫から選定してもらいます。しかし朗読作品として使用してはいけない作品もあるので各自確認しながら抽出箇所を選んでもらうことになります。
著作権の消滅した作品や「自由に読んで構わない」とされた作品を集めたインターネット上の図書館のようなサイトです。下記URLから詳細をご確認ください。
青空文庫:https://www.aozora.gr.jp/
著作権切れの作品は
「著作権の消滅した作家一覧」 https://www.aozora.gr.jp/siryo1.html に掲載されている作家の作品を指す。 この条件に合わない作品は選ばないこと。
直接審査結果に関わることはありません。審査員によって作品に関する情報量が違い、審査が平等に行われない可能性があるため、事前にあらすじを準備してもらいます。
朗読部門 審査基準について
大会では独自の審査基準を取り入れることにしました。この審査基準は基本的にNHK杯全国高校放送コンテストに則って作成されています。
両部門100点方式で審査をします。審査が円滑に進むよう、それぞれの項目で点数の上限を設けました。
以下は審査項目の説明、点数の上限の紹介(かっこ内)です。
「内容について」が40点、「アナウンスの技術について」が60点で合計100点です。
失格行為
- 提出物(音源、原稿、あらすじ)のいずれかが欠けている
- 提出した原稿と音源との間に本文の相違がみられる
- 規定時間(1分30秒~2分)が守られていない
- 規定外の作品を朗読する(青空文庫以外の作品、青空文庫内でも朗読を禁じられている作品等)
- 原稿の改変(文の途中から抽出、脱落等がある
- 音源に何かしらの加工(音声チェンジャー、編集等)があった場合
内容について(全40点)
(1) 作品の選定(20点)
朗読に向く作品、技量や声の質に見合った作品かどうか判断。
技量に見合わない作品を選ぶ⇒-5
声質に見合わない作品を選ぶ⇒-5
(2) 抽出の仕方
会話文と地の文の割合も確認する。(地:会話は7:3~8:2程度の割合)
抽出した意図が伝わらない(抽出箇所内のストーリー性がない)⇒-1~5
地の文と会話文の割合が適当でない⇒-5
登場人物の人数が適当でない⇒-5
始まり方、終わり方が適当でない⇒それぞれ-3
朗読の技術について(全60点)
(3) 発声(7点)
声が出ているか、場面の雰囲気にあった声づくりをしているか判断。
声のボリュームにばらつきがある(表現として成立していれば除外、環境上の問題だと判断できる場合も除外)⇒-3
声を前に届けようという意識を感じられない⇒-3
全体を通して場面の雰囲気に合う声作りができていない⇒-3
(4) 発音(7点)
項目名通り、甘噛みや吹かれ等発音の甘さや違和感はないか判断。
(5) アクセント(7点)
アクセント辞典を確認しながら正しいアクセントか判断。
(6) 内容把握(9点)
物語の大筋を把握して朗読しているかをあらすじとあわせて判断。
登場人物の性格、場面の雰囲気を捉え、情景が容易に思い浮かぶかを声色やトーンを中心に評価する。
原稿内の動き(映像)が途中でちぐはぐになる⇒-3~5
あらすじと全く一致しない読みである⇒-5
あらすじと少しずれた読みである⇒-2
登場人物の読み分けができていない⇒-4
地の文と会話文の区別がつかない⇒-4
(7) テンポ(8点)
読む速度が適切かどうか判断。特に間延びしていないかを確認する。
読むテンポがやや早いor遅いと感じ、違和感がある⇒-5
一部読むテンポが早すぎるor遅すぎる⇒-3
終始テンポが一緒⇒-5
(8) イントネーション(7点)
「始高終低」「頭高尾低」「読み下し」ができているか判断。
文中でうねったり、何度も高い音で入り直したりするのは基本NGだが例外もある。(方言など)
うねりが多数見られる場合⇒-5
文中何度も高い音で入りなおす⇒-4(違和感なければ除外)
一部うねりがあった場合各⇒-1
(9) ポーズの取り方(8点)
聞いていて心地の良い間か、物語が理解できる間かどうか判断。
会話文と地の文の間、場面転換の間、心情文と情景文の間等を確認する。
ポーズが足りないorありすぎると感じる箇所が多数見受けられる⇒-5
ポーズが足りないorありすぎると感じる箇所が一部ある各⇒-1~2
ポーズはあるが、情報をかみ砕くのに適切な間でない、相槌を打ちづらいような間である⇒-3~5
ポーズが均一⇒-5
(10) プロミネンス(7点)
重要な言葉が強調されているか判断。
物語の流れ、登場人物、心情、状況が際立って聞こえてくるかを確認する。
一部強調欠けている各⇒-2